令和7年2月1日(土)。開館を目前に控えた鳥取県立美術館(倉吉市)に,鳥取県内公立高校・私立高校の生徒が続々と集結。令和6年度鳥取県教育研究大会(鳥取県探究成果等発表会)に参加するためです。
集まったのは,予選等を踏まえ選抜された県内高校の精鋭達。自分の心をつかんで離れない「もっと知りたい!」「研究したい!」といった知的好奇心や課題意識に応じて,どの生徒も本気で探究活動に取り組んできました。
2月1日(土)の大会は,その課題研究等の成果を発表し,県内の同世代高校生と学びあう場。明るく開放的な美術館の雰囲気に後押しされ,どの生徒も精いっぱい,自分(達)の取り組んできた研究の魅力や可能性について熱く語りました。
最優秀賞に輝いた理数科2年生5名が取り組んだのは化学分野の研究です。研究タイトルは「キチンナノファイバーの菌類・細菌類との戦いの記録~実用化を目指して~」。
先日,このHPでもお伝えしたとおり,5名が取り組んだ研究は,理数科2年生の課題研究(理数探究)として取り組んできたものです。科学的な手法や検証が適切に踏まえられているだけでなく,研究過程でひらめいた高校生らしい斬新なアイデアも組み込まれた研究内容とその結果だけでなく,プレゼンテーションのできばえや発表時の態度等に関しても,審査員から高い評価をいただきました。
〈発表の様子〉(2年生グループ)
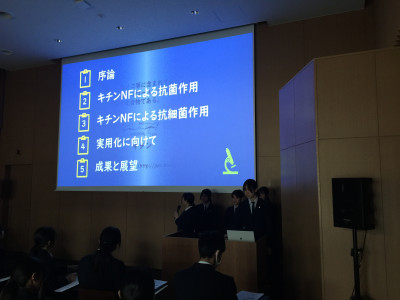
優秀賞に輝いた科学部1年生1名が取り組んだのは生物分野の研究。「鳥取県千代川水系におけるテナガエビの調査報告」と題してその研究成果を発表しました。
今回の発表は1年間におよぶ実地調査と研究をまとめたもので,先行文献・研究にはない新しい発見を含む高度な内容が報告されました。調査の過程で自らにわいた疑問や不思議について,科学的な研究アプローチを適切に踏まえて地道に研究を続けてきたその取組及び成果が高く評価されました。
〈発表の様子〉(科学部1年生)

鳥取東高校は,自ら学び,自ら考え,自ら果敢に行動する力や探究する積極性を生徒に育てたいと考え,生徒一人ひとりの思いや可能性を大切にして教育活動に取り組んでいます。
このため,生徒も教員も,学習,部活動,学校行事の「三兎」を追うを共通言語として互いを刺激しあい,互いに学びあいながら学校生活に没頭しています。
このうち,探究活動(学習)や課題研究は,こうした大会やコンテストで好成績を修めることをゴールとするものでは必ずしもないと考えています。
県大会に駒を進められなかった本校生徒の活動や研究にも,その取組に将来性が感じられたり,社会をよりよくする開発等につながるのではないか…と心が躍るような感覚を覚えたりする,そんなものがたくさんありました。
それ以上に大切にしたいと本校が思うのは,一人ひとりが興味関心を持った事柄について,それぞれが有する教養や知識をフル活用したり,探究活動や課題研究にふさわしい手法を学び,運用したりしながら取り組んできたそのプロセスで,生徒がリアルに感じたり,気づいたり,学んだりしてきたことです。
「実際にやってみないとわからないことがたくさんあるんだ」と気づく生徒がたくさんいました。地域連携や高大連携をとおして,「自分(達)は実にたくさんの人々に支えられ,助けられているのだ」ということを実感した生徒もいます。人の思いがかたちになることの凄さと尊さに思いを馳せた生徒も少なくありません。こうした気づきが生徒にもたらす教育力は計り知れない。本校はそう考えています。
他方,上位大会・コンテストに出場したり,そこでの活躍を目標にすることは,生徒にとって大きなモチベーションになるだけでなく,学びの質を高めたり研究の精度を高めたりするのも事実です。
思うような実験結果が得られなかったり,いくら調査・研究しても謎ばかりだったりする…そんな苦しみや悩みから逃げることなく,粘り強く探究し続けるその営みそのものが大きな舞台で評価される。この喜びは,苦しんだからこそ得られるものであり,その後のキャリアや人生を支える力にもなります。

鳥取東高には毎年,ポテンシャルの高い生徒がたくさん入学してきます。「三兎」を追う学校生活の中で,自ら「場」を求め,「やってみよう!」と思うことに果敢にチャレンジする過程で得られるたくさんのチャンスをよりよい自分づくりに生かしていく…そんな生徒をたくさん育てたいと,今あらためて思っています。
日頃から本校生徒の探究活動(学習)や課題研究(理数探究)にご協力くださっている地域のみなさま,そして関係大学の先生方,本当にありがとうございます。どうぞこれからも熱いご支援のほど,よろしくお願いします。
(https://tottori-moa.jp/より)