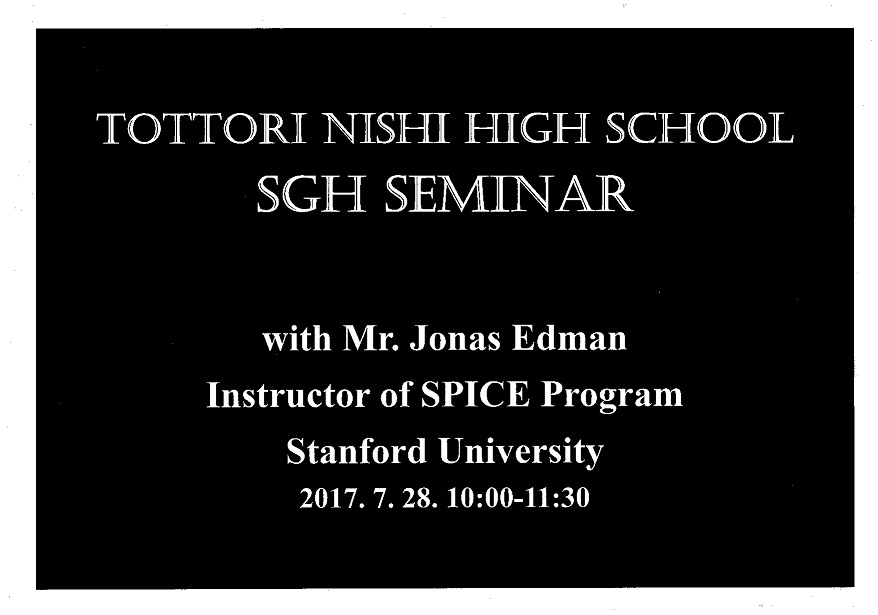10月6日(金)放課後、国連人口基金(UNFPA)イラク・バグダッド事務所の谷口英里さんをお迎えし、第6回SGHセミナーを実施しました。モンゴル、ネパール、ケニア、ソマリア、イラクで勤務された体験談、高校から大学にかけて国連職員になるためにどんなことを考えて実践されてきたかという話、またジェンダーに基づく暴力対策専門官として女性のエンパワーメントを各国政府やNGOと連携して構築する話など多岐にわたる話題を提供して頂きました。座談会ではジェンダー問題に関わる質問が多く、活発な話し合いの場となりました。

研修初日。オリエンテーション、授業参観、キャンパスツアーなど様々な活動に参加しました。
無事アデレードに到着しました。迎えに来ていただいた各ホストファミリーの家に向かいました。
無事シドニーに到着しました。オペラハウスの周辺でインタビュー活動。

今日の出来事
鳥取を出発して無事羽田空港に到着しました。
これから10時の飛行機でシドニーに向かいます。
9月23日(土)
第5回のSGHセミナーとして、智頭町のアフリカの田んぼ稲刈りを実施しました。5月に田植えをした田んぼで、実った稲穂を皆で鎌を使って刈り取っていきました。ベナン、ウガンダ、ナイジェリア、メキシコ、モンゴル、マレーシア、中国、韓国など世界各国から鳥取大学に来ている留学生、地元智頭町の人々、子供たちと一緒に、秋の晴天のもと作業を行いました。午後は鳥取大学の学生ボランティア主催の交流会で各国に関連するクイズをしたり、餅つきを楽しんだりしました。刈り取られたお米はコントリビューションの会を通じてケニアの児童養護施設マトマイニチルドレンズホームへ贈られる予定です。

9月20日(水)
野の花診療所 院長で本校ご出身の徳永進先生を講師としてお迎えして「著者と語る講演会」を実施しました。この講演会は希望生徒が運営の主体となって実施をしているもので、今年で24年目を迎えました。前半は「いのちのそばで」と題した講演会、後半は生徒代表による質問会を実施しました。徳永先生の楽しい語り口で会場全体が笑いに包まれる場面や、臨床の現場の話に目に涙を浮かべ、いのちの最期のあり方に考えをめぐらせる場面など、様々な生徒の表情が見えました。全体を通じて、自分の種(たね)をどこで見つけどう咲かせるか、そしていのちの「矛盾」を豊かにもつことについて考えを深めることができました。

本校生徒がカンボジア高校生と交流しました。これはイオン1%クラブ主催のティーンエイジアンバサダー高校生交流事業によるもので、日本と海外の高校生が、政府訪問などの「大使活動」、授業体験やホームステイなどの「交流活動」、文化遺産への訪問や伝統文化を体験する「歴史・文化活動」を通じて、互いの国の歴史や文化を理解し、友好親善を深める活動です。今回はカンボジア高校生が日本を訪れ、「大使活動」として在日カンボジア大使館や外務省などを表敬訪問し、「交流活動」として本校での授業や書道、茶道を体験し、本校生徒宅にホームステイをしました。また「歴史・文化活動」としてカンボジア史第一人者であり「ラモン・マグサイサイ賞」受賞者の上智大学アジア人材養成研究センター所長石澤良昭教授よりアンコールワット遺跡の修復についてご講義いただき、倉吉賀茂神社にて浅野温子氏による「打吹天女伝説」読み語りを鑑賞しました。11月には本校生徒がカンボジアを訪問し、現地で表敬活動及び交流を行います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea1/kh/page25_001011.html


7月28日(木)
アメリカ合衆国スタンフォード大学のヨナス・エドマン先生をお迎えして、第4回のSGHセミナーを実施しました。今回のテーマは「Helping Others」でした。テロや危険な犯罪現場で他者を助けるためにとった行動で被害者が出た場合などを想定したディスカッションを行いました。議論は白熱し、人道的、倫理的あるいは哲学的な話題に発展し、参加した生徒自身も「英語でこんなに深く議論が出来るとは思わなかった」と感想をお互いに述べあい、貴重な時間をエドマン先生と共有することが出来ました。参加生徒の一部は今年度8月末から始まるスタンフォード大学とのオンライン授業「グローバルリーダーズキャンパス」に参加して議論を継続する予定です。