令和5年度 後期TEAS研修会を実施しました!!
司会進行は、管理環境委員長の岩谷くんと副委員長の山根さん。

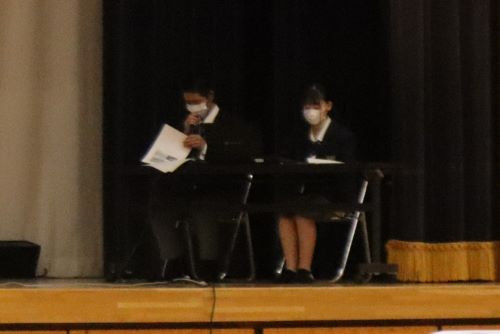
まずは、岩美高校の「環境宣言」の基本理念を説明し、改めて環境学習・環境配慮推進の意味を伝えました。
そして、地球温暖化がもたらす自然災害の実例を写真とともに紹介し、その恐ろしさを強調しました。

岩美高校が毎年取り組んでいる活動について、可燃ごみの削減は順調に進んでいるが、電力使用量においてはまだ課題が残っており、特に夏季のエアコン利用が一因であると報告しました。そして、エアコンを使用する代わりにこまめに照明を消すことで電力の無駄遣いを減らす取り組みを呼びかけました。

また私たちができることとして、大きく2つの提案がありました。
1つ目は、学校生活で出る可燃ゴミの量を減らし、燃やす際に発生する二酸化炭素の削減に貢献する。
2つ目は、裏山の雑木林を整備することが豊かな植物の育成につながり、結果CO?削減に寄与することできる。
最後に、12月4日に予定されている「裏山整備」への参加を呼びかけました。
研修会は環境への理解を深め、実践的な活動への参加を奨励する素晴らしい機会となりました。
本日は、職員室からの出火を想定した避難訓練を行いました。
火災を告げる放送から、点呼が終わるまで、3分44秒。
押さず、慌てず、しゃべらず、速やかにの"オアシス"を守って避難できていました。

今回の避難訓練について辻中校長は、「平成28年の鳥取中部地震のちょうど1週間前に避難訓練をしていたので、実際の災害時にスムーズに避難ができた。」と当時を振り返り、避難訓練の大切さを強調しました。

本日のLHRの時間は、講師に一般社団法人 株式会社Psychoro(サイコロ)の谷口さんに、「充実した生活に向けたメンタルヘルスのお話:みんなの"ガッツ"をうまく活かすために」をテーマに講演をいただきました。

講演で谷口さんは、「ストレスは脳の負担。放っておくと体の病気にもつながる。いろんな不安を考えてしまっている状態の時は、脳を休めることが大切!」とお話しされました。
また、3つのストレス対処法を紹介され、これらの対処法をバランスよく取り入れ、不安(ストレス)を理解し、自信に変え向き合っていくことが重要であると述べられました。
■3つのストレス対処
【1】問題の解決に取り組む
【2】考え方をかえてみて気持ちを落ち着ける
【3】問題から逃げる。考えない。

講演を聞いた後、生徒会長の内田君が「いきなり大きな目標を立てるのではなく、出来ることから無理なく始めていくことも大切だと理解しました。今日教わったストレスの対処法を生活に活かしていきたい。」と感想と謝辞を述べました。

本日、令和5年度 岩美高校 後期生徒総会が行われました。
議長は、3年生の河口くんと星見くんが務めました。


<生徒総会の内容>
【1】令和5年度(2023年)前期行事および活動報告
【2】虹嶺祭 アンケート結果について
【3】令和5年度(2023年)前期執行部員 解任
【4】令和5年度(2023年)後期執行部員 紹介と承認
【5】令和5年度(2023年)後期行事および活動計画と承認
【6】閉会
令和5年度(2023年)前期行事および活動報告では、前期生徒会長の福間さんが前期に取り組んだ生徒会行事を振り返りました。

続いて前期に行われた「虹嶺祭」アンケート結果については、前期副会長の中野くんが発表。反省点や、今後の要望などたくさんのアンケート回答を報告しました。

その後、令和5年度(2023年)前期執行部員解散、後期執行部員の紹介と承認が行われました。
後期の執行部員ひとりひとりの紹介をした後、令和5年度(2023年)後期行事および活動計画の提案を、後期生徒会長の内田くんが発表し、承認されました。



生徒たちの協力によってスムーズな生徒総会となりました。
3年3組の10名が、「子ども文化」の授業の一環として、岩美町立みなみ保育所を訪れ、園児たちと共に楽しいひと時を過ごしました。
10名の生徒は、3~4人のグループに分かれ、保育園の年長、年中、年少のクラスに分かれて実習。
園児の年齢ごとに異なる遊びのプランを考え、それらに必要なおもちゃや小道具を手作りで準備して、本日を迎えました。実習で使用するおもちゃは、園児たちの興味を引きつけるように工夫され、イラストや色合いが施されていました。



生徒が考案したプランは、園児たちが元気よく大きな声をだして体を動かす遊びや、ジェスチャーなど表現力を磨く遊びなどがあり、園児たちの反応も大変良好でした。
はじめは高校生の生徒も園児もお互いに少し緊張している様子でしたが、遊びがスタートするとすぐに距離が縮まり楽しい時間を過ごすことができました。




帰りのバスでは、パワフルな園児たちに圧倒されて「疲れた」と口に出ていましたが、元気いっぱいの園児たちと楽しいひと時を過ごせて、生徒たちの顔は優しさに包まれていました。

岩美町立みなみ保育所の園児の皆さん、先生方、本当にありがとうございました。
3年3組 福祉類型の介護福祉実習 第5回目!
本日のテーマは「手浴・足浴・洗髪」。難易度が一段と上がりました。

入浴が難しい方のために自宅でできる部分浴の学習では、身の回りにあるアイテムを工夫して使います。
用意したのは、洗面器、かけ湯用のペットボトル(2リットル)、防水シーツ(ビニールシートや大きめのゴミ袋)、タオル、バスタオル、シャンプー・リンスなど。洗髪をするためのケリーパッドも、新聞紙、バスタオル、ビニール袋を使用して手作りしました。


〇手浴



〇足浴


〇洗髪




生徒は、利用者役や介護者役になり、より良い介護環境や利用者との信頼を築くため、声かけや会話にも意識しながら実習を行い理解を深めていました。
介護福祉の授業では今後も、さまざまなテーマでの実習が予定されています。
本日のLHRは、人権教育について。
公開授業となった本日のLHRは、複数の保護者の方々も見学にいらっしゃいました。
学年ごとにテーマを設定して、各クラスが様々な問題について話し合いました。
1年生のテーマは「いろんな価値観」
差別や偏見を見抜く力と他人の立場や心情を共感的に理解する力を養い、互いを尊重しながら信頼関係をむすぶことのできる環境を作ることを目指します。


2年生のテーマは「身近な差別」
身近に存在する差別に対し問題意識を持ち、自分の中にある差別意識に気づくことともに、差別解消に向けた行動がとれることを目的とします。



3年生のテーマは「差別解消への取り組み」
自他の自由や権利を尊重する態度を養い、自らの変容と言動が社会を良い方向に変えることにつながるという見方および実践を目指します。



生徒たちは、話し合いや意見をワークシートに落とし込み、授業を通して差別に対する正しい理解や良好な人間関係への配慮などを学びました。
本日は、日本の調理専門学校の中で一番の人気を誇る「辻調理専門学校」から、講師に柳さん、針本さんをお迎えして、3年3組のフード類型5名と、2年3組20名が調理実習を行いました。
午前中、3年3組「栄養と食文化」の授業で5名に指導してくださったのは、辻調理専門学校で西洋料理を教えておられる 榊さん。なんと、5つのメニューを教えていただきました。
メインは、牛サーロインのステーキソース・ベアルネーズ(Faux-Filet de boeuf Saut? Sauce b?arnaise-フォ フィレ ド ブフ ソテ ソース ベアルネーズ-)、こねるパンとこねないパン、副菜は、きのこソテとじゃがいもグラタン。デザートにガトー・ショコラ コアンドル風。

調理の前に、講師の榊さんが一通り作り方を実践され、その包丁さばきや調理の手順の華麗さに生徒たちは目を奪われていました。







メインのステーキに、本日ご準備いただいたお肉は4種類!
黒毛和牛、交雑肉、国産牛、オーストラリア産。
それぞれの肉の特徴や値段などの説明もあり、生徒たちは興味深く耳を傾けていました。
生から焼く肉と、あらかじめ低温調理されたミディアム肉、肉の違いに加え、焼き方の違いによっても、味が変化することを学びました。



実践では、細かな指導いただき、5品完成!






食事の時間は、達成感と満足感でみんな喜びの表情を浮かべていました。


生徒からは、「なぜ、料理人になったのか」「お店を開くにはどうしたらいいか」などという質問があり、榊さんは、ご自身の経験をもとに力強くお話しされました。

午後からの2年3組「フードデザイン」の授業を指導してくださったのは、辻調理専門学校で製菓を教えておられる 針本さん。
「タルト・モンブラン」を教わります。


針本さんも、一通りの手順を実際に作りながら説明され、まるでマジックをみているかのように、お皿に芸術的なモンブランが出来上がりました。
秋のスイーツらしく、もみじやイチョウの葉を型取った食べられる飾りも素敵です。

栗のペイストを混ぜる際の注意点や、絞り袋から生クリーム、マロンクリームを絞りだすときのコツなども細かく指導いただきました。







生徒たちは、チョコレートやジャムなどで、プレートにイラストや名前などを書き、自分のために作るモンブランを苦戦しながらも楽しみつつ作っていきました。



本日の実習は、プロの調理のプロセスを実際に体験し、その技術を実感する絶好の機会となりました。
本日、鳥取県内東部の中学から進路指導の先生方にご参加いただき、和やかな雰囲気で学校説明会開催されました。
鳥取県内外の21の中学から3年生担当の先生や進路指導担当の先生方にご参加いただき、和やかなムードで会が進みました。

学校説明会では、辻中校長がプレゼンスライドを使い、特色ある岩美高校の授業や取り組みを紹介しました。
手話の授業や調理実習、介護福祉、そして山陰海岸ジオパークが近くにあるという立地を生かした学習環境の中で、生徒たちは自信と自己有用感を養い、日々成長をしていると語りました。
続いて、三好教頭からは岩美高校の進路指導と生活指導について、詳細な説明がありました。
最近の進学状況や、岩美高校での授業と生活指導を通して驚くべき成長を遂げた生徒たちの実例も紹介し、学校の熱心なサポートがどれほど有益であるかを示しました。

最後に、中学ごとに個別の面談が行われ、質問や疑念を解消し、より詳細な情報を得る機会を持ちました。

3年3組 福祉類型の介護福祉実習 全7回のうち、今回は第3回目!
本日のテーマは「オムツ交換と清拭」です。講師は、岩美町社会福祉協議会 前田さんです。
第2回目では、「衣類の着脱」を学習し、その際にもおこなう「清拭」や「オムツ交換」。
体を拭く時、心臓に向かって肌にダメージを与えないよう優しく行うなどといったポイントや特に注意するべき体の部位など細かく指導いただきました。


さらに、オムツ交換では、オムツがどれくらいの水を吸うことができるのか、水をオムツに注ぎ実験。
液体を吸収したオムツの状態を実際にさわるなどして深く理解しました。想像以上の吸収力に生徒たちは驚いていました。


また、服の上から実際にオムツを付けた感覚を体感したり、ペアになって寝たきりの方へのオムツ交換を行えるよう練習したりと、学生たちは実践的なスキルを磨いています。

福祉類型の介護福祉実習は、介護の分野での重要な技術を習得し、将来のキャリアに備える生徒たちにとって有意義な授業となっています。