9月3日、1年生の必読図書である『疑似科学入門』(岩波新書)の著者である池内了さん(名古屋大学名誉教授)にお越しいただき、著者講演会を実施しました。
今回の講演会では「3・11の衝撃-福島原発事故から考えたこと」という演題で、東日本大震災及び福島原発事故による「安全神話」の崩壊から、これからの科学や科学者のありかた、そして未来に向けて我々はどのように「科学的に考える」ことをすればいいのか、ということについての話をしていただきました。また、科学だけでは解決できない問題(トランスサイエンス問題)も多くあり、哲学・倫理・社会学などいろいろな視点から物事をとらえて論じていく必要性についても語られました。
講演の様子

生徒代表謝辞・花束贈呈
また、講演会後に大会議室に会場を移して実施した座談会では、50名を超える参加者の中から多数の質問が寄せられ、大変有意義な会となりました。今回の講演会の内容からだけではなく『疑似科学入門』をはじめとした著作の内容からの質問など、さまざまな内容の質問がなされ、その中で「あらゆることについてすぐに信じたりすぐに答えを求めたりせず、まずいろいろな意見や見解を集めて“裏にあるものは何か”を考える中で自分なりの筋道や答えを見つけることが大事」「科学に携わる者は、人々の幸福を望み、精神的な生活を豊かにすることができ、自分がしていることについて常に自問自答ができることが必要とされる」など、我々のこれからの学びの姿勢や生き方についても大変考えさせられるお話もありました。
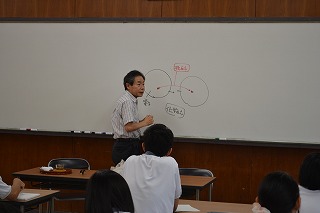
座談会の様子
池内さんには大変ご多忙にも関わらず今回の講演会に来ていただいたこと、また長時間にわたり貴重なお話をしていただいたことに、倉吉東高の生徒職員一同、多大なる感謝の意を表する次第です。
9月3日(水)午後、著者講演会を実施します。
今年度の講師は、1年生の必読図書『疑似科学入門』の著者である、名古屋大学名誉教授の池内了(いけうち・さとる)さんです。
図書館では現在、池内さんの著作や、講演会で取り上げていただく原発に関する内容の資料を多数集めた特設展示を実施しています。また、教室棟にも、講演会前にぜひ読んでほしい雑誌記事等を集めた掲示板を設置しています。本は貸出もできますので、この機会にぜひ読んでみてください。
そして、展示と合わせて池内さんについての情報等をまとめて紹介した「池内了さんと科学について考える」というライブラリー・ナビ(じゃばら折りのリーフレット)を作成しました。内容は、経歴や著作からの抜粋等をまとめたもので、これを読んで講演会に臨めば理解がより深まると思います。図書館の特設展示コーナーと教室棟の掲示板のどちらにも設置していますので、興味がある人はぜひ手にとってくださいね。
図書館前の特設展示の様子
教室棟の掲示板(生徒もよく見てくれています)
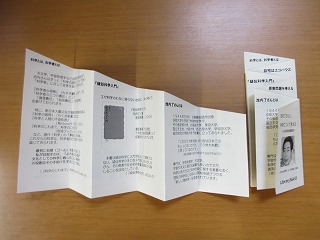
これがライブラリー・ナビです
★平成26年度 著者講演会について★
日時:9月3日(水)13:15~14:55
場所:倉吉東高校体育館
講師:池内了氏(名古屋大学名誉教授)
演題:「3・11の衝撃ー福島原発事故で考えたこと」
7月30日(水)、中部の高校から生徒13名が集まって「図書委員交流会」(主催:鳥取県高等学校図書館教育研究会中部支部)が開催されました。本校からも図書委員の生徒(前年度の図書委員を含む)4名が参加しました。
2部形式のプログラムで行われ、まず前半は今井書店の松本さん・尾上さん・中井さんを講師に迎えて、本を紹介するPOPの作成講習会が行われました。最初にPOPの作り方のコツなどの説明がなされ、それを受けて参加者が各自紹介したい本のPOPを実際に作成しました。限られた時間ではありましたが、皆思い思いに工夫してPOPを作成していました。
POPを作成している様子
どれも工夫を凝らした力作ばかりです
(図書館でただいま展示中!)
後半は、参加者がそれぞれ自分の学校の図書館の様子や図書委員の活動を紹介する情報交換会が行われました。本校の図書委員も、東高図書館の様子や、返却期限しおり作りや先生方のおすすめ本紹介などの委員会活動を紹介しました。他校の事例もどれも面白く参考になるものばかりで、参加者にとっていい刺激になった有意義な会となりました。
本校の活動を紹介する図書委員の様子
明日から始まる第13回国際高校生フォーラムのために、韓国の安養高校の皆さんが来日されました。
図書館では今日のために、歓迎の気持ちをこめて韓国の文化に関する展示を実施しています。
鳥取県立図書館の環日本海交流室から韓国に関する図書やパンフレット、鳥取を韓国語で紹介したパンフレット、日本で大人気の小説や絵本を韓国語に翻訳したものなどをお借りして展示しています。
また、図書やパンフレットだけではなく、鳥取県国際交流財団から韓国の民族衣装や装飾品などもお借りして合わせて展示しています。
図書館での展示の様子
よく読まれている絵本や人気の小説が数多く翻訳されています
本日午後、東高に到着された安養高校の皆さんは、学校見学の際に図書館にも来館されました。交流担当の本校生徒の案内で一緒に展示を見て、韓国や日本の文化について情報交換をしていました(鳥取県を代表するゆるキャラ・トリピーが大人気でした)。また、交流担当の3年生がチマチョゴリを着て歓迎するなど、楽しい国際交流の時間となりました。
熱心に展示を見てくださる安養高校の皆さん
交流担当の生徒がチマチョゴリで歓迎!
6月20日放課後、図書館ゼミ「自己表現力を高める」を実施しました。
今回の講座は、生命倫理をはじめとする応用倫理学を研究しておられる広島大学大学院文学研究科教授の松井富美男先生に来ていただき、目前に控えた学園祭そして国際高校生フォーラムに向けて、プレコン委員を対象に今年のテーマ「医療問題と生命倫理」に関する講義とチーム別協議という形式で実施し、生徒や職員等60名を超える参加がありました。
前半の講義では、生命倫理についての視点や問題の捉え方、倫理学の役割の変化等、普段なかなか触れることのない倫理学の専門家ならではの内容に皆が熱心に聞き入っていました。
また後半は各チームに分かれて、松井先生から与えられたいくつかの「お題」をもとに、自分たちがプレコンに向けて考えていることについて話し合い、まとめを発表しました。どのチームも大変熱心に話し合いがなされており、最後の松井先生からの講評・指導助言では「いいところをつかんでいるチームもあって感心した」との言葉もいただきました。終了後も残って松井先生に質問をする生徒や話し合いをしているチームも多く、非常に熱気にあふれた会になりました。

講師の松井富美男先生

チーム別に話し合っています
話し合ったことをチームごとに発表

終了後も熱心に質問していました
図書館では毎月、「図書館ニュース」と「新着図書案内」を発行しています。
今年度第1号の図書だよりを作成しました。今回の内容は、教育実習生の先生8名のおすすめ本紹介です。実習期間もあとわずか、せっかくの機会なのでおすすめ本を手にとって、いろんな本の話ができるといいですね。
図書館では毎月、「図書館ニュース」と「新着図書案内」を発行しています。
「新入生にも図書館をどんどん利用してほしい! 本を読んでほしい!」との思いから、1年生を対象に情報の授業の中で図書館オリエンテーションを実施しました。
まず、図書館の利用方法やオンラインデータベース「朝日けんさくくん」の利用についての説明を行い、昨年度図書館でよく借りられていた本の紹介をしました。また合わせて朝読書で読む必読図書の紹介を行い、朝読書で必読図書を読むことの意義について話をしました。東高で過ごすこの3年間、ぜひ読書(特に朝読書)の時間を大切に過ごしてほしいと思います。

図書館の利用についての説明
案内の後は、図書館オリテン名物・先生方(村岸、段塚、川北、岩野、前田)による絵本『たまごにいちゃん』の読み聞かせ。少し緊張気味だった生徒たちの気持ちもほぐれ、その後は皆思い思いに図書館を探索、興味を持った本を見つけて借りてくれました。また、授業の最後には情報担当の村岸先生からのおすすめ本の紹介もしていただきました。
これからも、新入生の皆さんには、たまごにいちゃんのように「自分の殻を破って」がんばってほしいと思います。そしてこれからも、ぜひ気軽に図書館を利用してくださいね♪

村岸先生によるおすすめ本の紹介

これからもどんどん本に親しんでくださいね
参考:
倉吉東高図書館の蔵書検索はこちらから(校内のパソコンからのみ利用できます) オンラインデータベース「朝日けんさくくん」の利用はこちらから(校内のパソコンからのみ利用できます)
本日、春休みの課題である、医療問題と生命倫理に関する小論文の品評会を行いました。
春休みの小論文課題は、生徒たちが学園祭プレゼンテーションコンテスト及び国際高校生フォーラムに目的意識を持って関わることができるように、昨年度から実施している取り組みです。
今回の品評会では、昨日のOB講演会の内容を取り入れつつ、生命倫理と医療の問題等について全校で考えました。それぞれが書いた小論文の内容をクラスや学園祭のチーム内で共有し、今後も更に議論や考察を深めていってほしいと思います。
1年生は初めての小論文・初めての品評会でしたが、慣れない中にも皆が大変熱心に取り組んでいました。

班の中で出た意見を代表して発表(1年生)
2年生、3年生は、これまでの品評会での経験を生かして取り組んでいました。特に3年生は、これから中心になってプレコン及びフォーラムを進めていく立場として大変意欲的に取り組む姿が見られました。

それぞれの小論文を読み、論点のポイントを整理(2年生)

班で出たキーワードや意見をボードに記入し、皆で共有(3年生)
今後、プレコンやフォーラムに向けて本格的に動き出していきます。直接的に関わる委員や担当だけでなく、みんなで生命倫理について主体的に考え、今後に向けて実り多い取り組みにしたいですね。